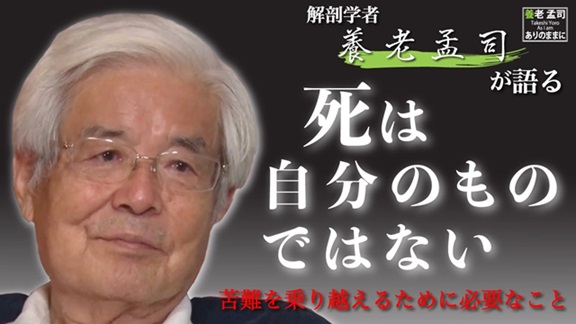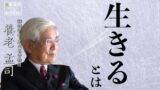㊲人生の最終回答
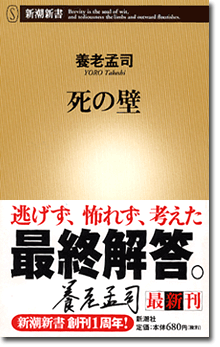
いよいよ「死」について取り上げるが、今回は養老孟司先生の著書「死の壁」を中心に、釈尊のことばを引用しながら書いて行きたい。
「死」という人生の最終回答を書くので、何回かにわたるがお付き合いいただければ幸いである。
思春期に「死」を考えた
私は思春期が始まった中学生の頃に、「自分はなぜ生まれて来たのだろうか?」と様々な思想哲学書や名著を読みながら自問自答する日々を送ったことを覚えている。
また、寝る前にはいつも「明日も生きています様に…」と祈る思いで眠りについていた時期があった。これは、死ぬことが怖かったのではなく、明日も生きたかったからである。
今は仏典解説や養老思想を研鑽するうちに、「死」について恐れもなく、この瞬間を含めていつでも死を迎えるのが人生なんだと納得している気がする。
ただ、猫さまと暮らしているので、私が先に死んだ場合は気になるが、死んでしまえばそれすらわからないからどうしようもない問いになる。
もちろん、あの世などあるはずがなく、身体という構造とりわけ脳構造も止まれば機能である意識は働かないので、自分が死んだことすらわからない。
今回は、養老孟司先生の著書「死の壁」の結論である終章「死と人事異動」を先に取り上げることにするが、その前にこの書の「あとがき」に養老先生と私が同じ幼少期の体験をしたことが書かれているので紹介したい。
人生が最初から死に接する
【養老】「私の人生の記憶は父親の死から始まっています。人生は物心つく頃から始まるとすると、私の場合には人生が最初から死に接していたことになります。」(死の壁/おわりに)
ブログ筆者の私も幼少の頃に父親が亡くなったので、記憶は病院で寝ている姿がうろ覚えにあり、亡くなる日に呼ばれて子供たち一人ずつに声をかけてくれたこと、火葬場で終わるのを待っていたこと。それが私の父親の記憶であり、私の人生もまた「死」というものがスタートになっている。
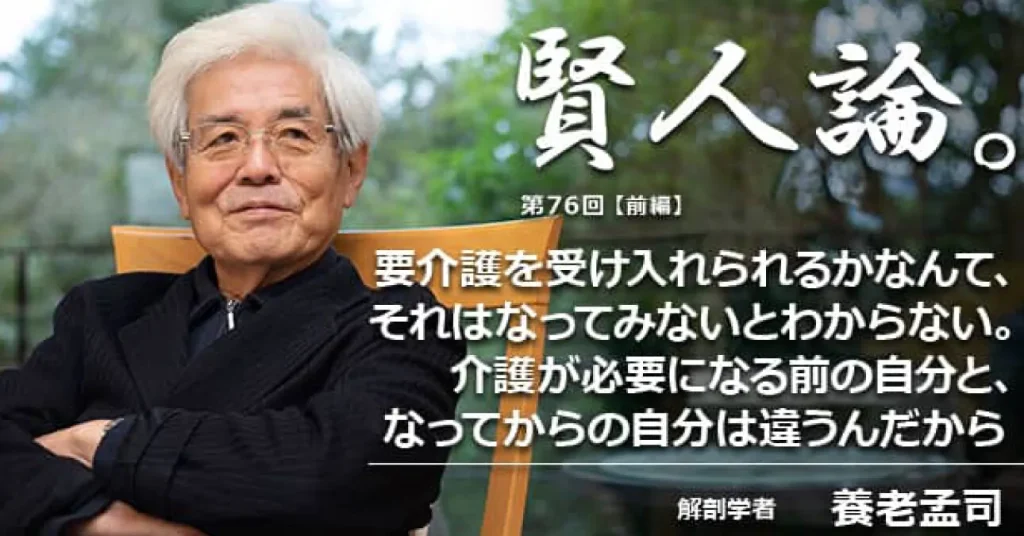
致死率100%
【養老】「いまでは多くの人が、死を考えたくないと思っているようです。もちろんそんなことを考えても考えなくても、さして人生に変わりはないはずです。結論はわかっているからです。」(死の壁:あとがき)
そして、
【養老】「なるべくしてなる。病気だって自然現象だから、なるようになる、と思っている。老いや病を敵視する人も意外に多いけれど、歳を取れば、老いるのは当たり前だし、いつかは必ず死ぬ。人の致死率は100パーセントで、この先どうなるかは、なりゆきです。」(同)
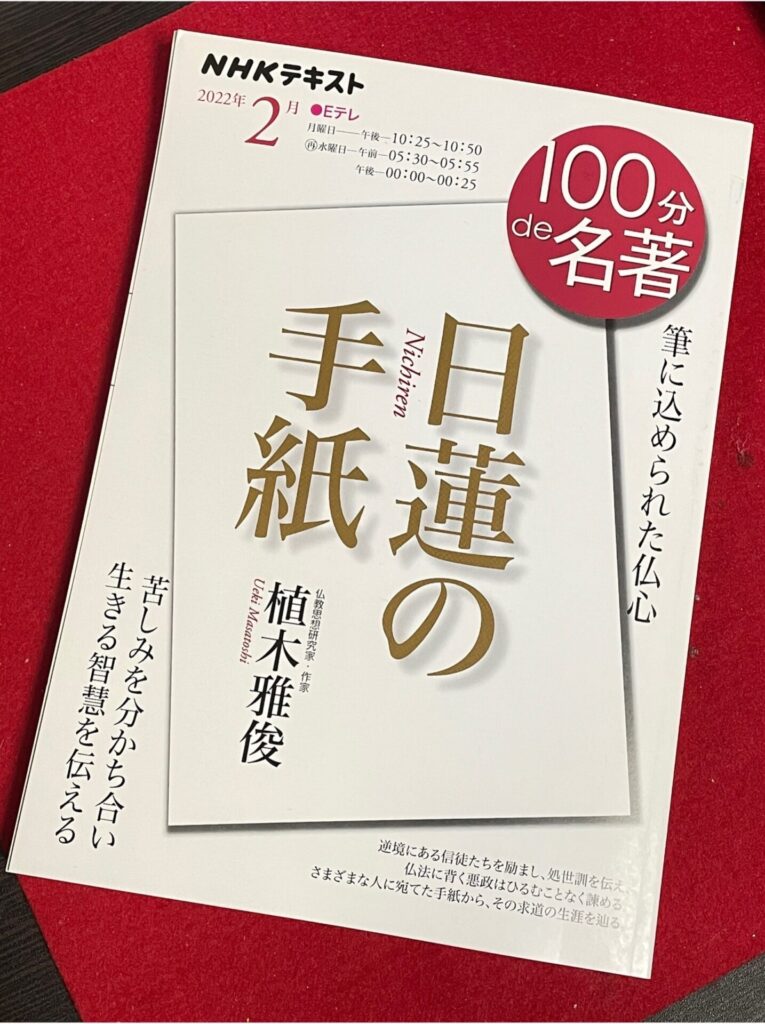
つまり、どんな人でも必ず死ぬことは確かだということだ。
鎌倉時代の日蓮も信徒への手紙の中で、「とにかくに死は一定なり」(死は必ず訪れる)と認めている。
また、別の信徒への手紙の中で、「先ず臨終の事を習うて後に他事を習うべし」といわれ、人生は無常であることを認識したうえで、死を迎えることを覚悟した生き方をすべきであると示している。
数多くの迫害に遭い、常に命を狙われ死と隣り合わせだった日蓮だからこそ、臨終の大事を解決することが何にも勝る優先事項であると考えたのではなかろうか。
釈尊の死についても、植木雅俊先生監修のNHKテキスト「100分で名著 日蓮の手紙」の中で、次の様に解説している。
「釈尊の死が近づき、悲しむ阿難(弟子)に対して釈尊は『阿難よ、悲しむな。私は既に、 生まれ、つくられたものは破滅するものであると説いたではないか』と語りました。自らの死に関しては、『人は死ぬものだ』と語っています。」(同p83)
死の恐怖は存在しない
【養老】「死について考えることは大切だとさんざん述べてきました。しかし、だからといって 死んだらどうなるかというようなことで悩んでも仕方がないのも確かです。
死について考えるといっても、自分の死について延々と悩んでも仕方が無いのです。そんなのは考えても答えがあるものではない。
したがって『死の恐怖をいかに克服するか』などと言ったところでどうしようもない。
それについてあえて答えるならば、『寝ている間に死んだらどうするんだ』と言うしかありません。
寝ている間に死んでしまったら、克服も何もあったもんじゃありません。意識がないんですから。
そこで悩むのは、そもそも『一人称の死体』が存在していると思っているからでしょう。
死ぬのが怖いというのは、どこかでそれが存在していると思っている、一人称の死体を見ることが出来るのではという誤解に近いものがあります。
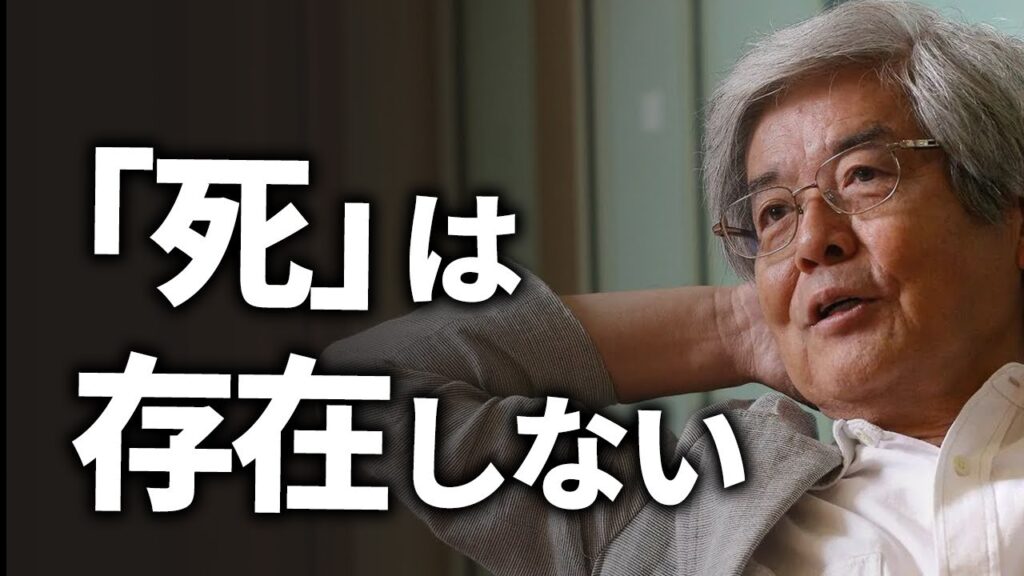
極端に言えば、自分にとって死は無いという言い方が出来るのです。
そうすると『(自分の)死とは何か』というのは、理屈の上だけで発生した問題、悩みと言えるかもしれません。これは「口」と似ています。
『口』とは何かというと、実は実体がない。そんな馬鹿なと思われるかもしれませんが、解剖学の用語からは削られてしまっています。
実際に解剖を少し考えればおわかりいただけるはずです。
たとえば唇は存在しています。それを指せばそこにあります。舌も存在しています。では唇でも舌でもない『口』はどこにあるのか。それは穴でしかない。実体がないのです。
建物の出入り口もそれと似ています。入り口は玄関だというかもしれません。しかし玄関の扉を取り外しても入り口はあります。かえって入りやすくなるくらいです。
こんなふうに自分の死というものには実体がない。
それが極端だというのならば、少なくとも今の自分が考えても意味が無いと言ってもよい。遺産の分割とかそういう死後の処理は別ですが。」(バカの壁/終章p165-166)
考えても無駄
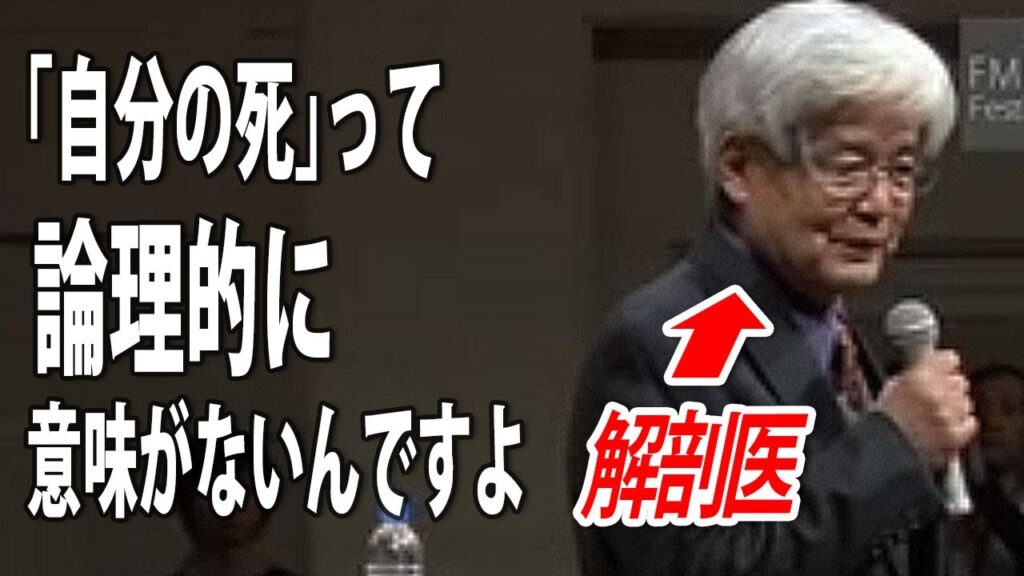
【養老】「死んだらどうなるのかは、死んでいないからわかりません。誰もがそうでしょう。しかし意識が無くなる状態というのは毎晩経験しているはずです。眠るようなものだと思うしかない。」(同)
つまり、そんなこと考えても無駄なんだと言っている。
釈尊もあの世の質問については、答えなかったとされるので、漢訳で「無記」となっている。
それは、形而上学的な確認のしようのないものに執着するよりも今を生きろと説いたからだ。
死後の世界は各国で捉え方が様々で、一神教の西洋では天国があると信じられている。
日本では死んだら閻魔様の裁きがあるという考えがあり地獄に落ちると強く言われて来た。
また、念仏を唱え死ぬと極楽浄土に行けるという思想が鎌倉時代に広まったので、誰もが挙って自殺したと言われる。
余談だが念仏では、女人成仏が説かれていないので、極楽浄土があってもそこは男性しかいない世界になる。冗談ではないが、そんな世界に行きたいとは思わないのは私だけではないはずだ。
中国の儒教では、「人間は死んだら、そういう人がいたという記録になる」という考えで位牌が作られた様だ。
【養老】「死というのは勝手に訪れてくるのであって、自分がどうこうするようなものではない。だから自分の死に方について私は考えないのです。」(同p168)
「終活」は無意味…

【養老】「死ぬ前に物などを処分して整理する「終活」が流行っていますが、僕はこれも意味がないと思っています。死という自分ではどうにもできないことに対して、自分でどうにかしようと思うのは不健全です。
生まれたときも、気付いたら生まれていたわけです。予定も予想もしていなかったことです。
死も『気が付いたら死んでいる』でよいのではないでしょうか。しかも死んでいることに自分が気付くことはありません。
僕もこれだけ虫の標本を持っていますから、『死んだらどうするんだ?』と訊かれます。そんなことは知ったことではありません。
今は箱根の別荘に保管していますが、ここも富士山が噴火したら一発で終わりです。
コレクションなど、一生懸命貯め込んでも、何かのきっかけで無に帰してしまうこともあるわけです。すべては諸行無常です。」(PRESIDENT Online 2023/04/29)