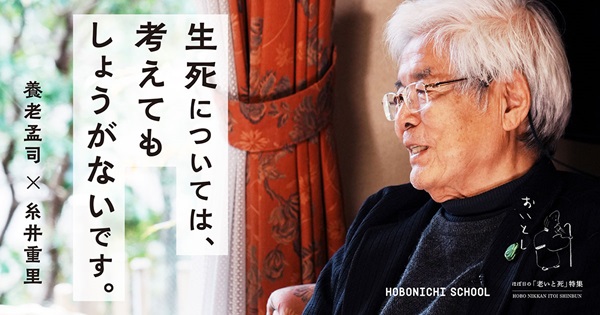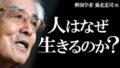㊴ボケは当人の問題ではなく介護の問題
前稿の続きで、「死の壁」から介護と死について取り上げる。
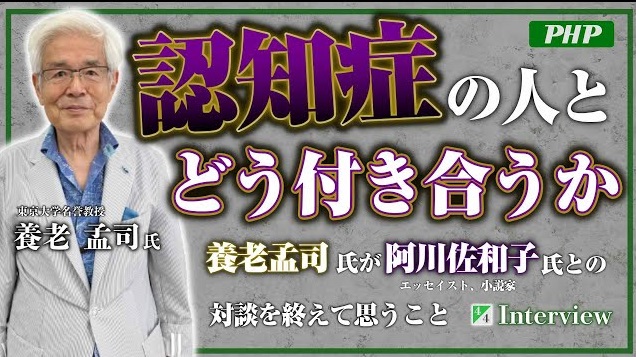
ボケて困るのは本人ではない
【養老】「老醜うんぬんというのはあくまでも他人が見ての話で、当人の問題ではありません。
講演でボケ問題について語ってくれという依頼をされることがよくあります。そのときは、最初に必ず『ボケて困るのはあなたじゃないでしょう』と言うのです。
ボケて困るのは子どもや奥さん、旦那さんです。それを心配する気持ちはよくわかりますが、それはボケ問題ではなくて介護の問題です。もちろん介護は大変な問題です。それは承知しています。
日本では、介護は身内がするのが当然だという風潮がいまだにあります。年寄りに変な扱いをしたら、「何だあの家は」と非難するような風潮です。
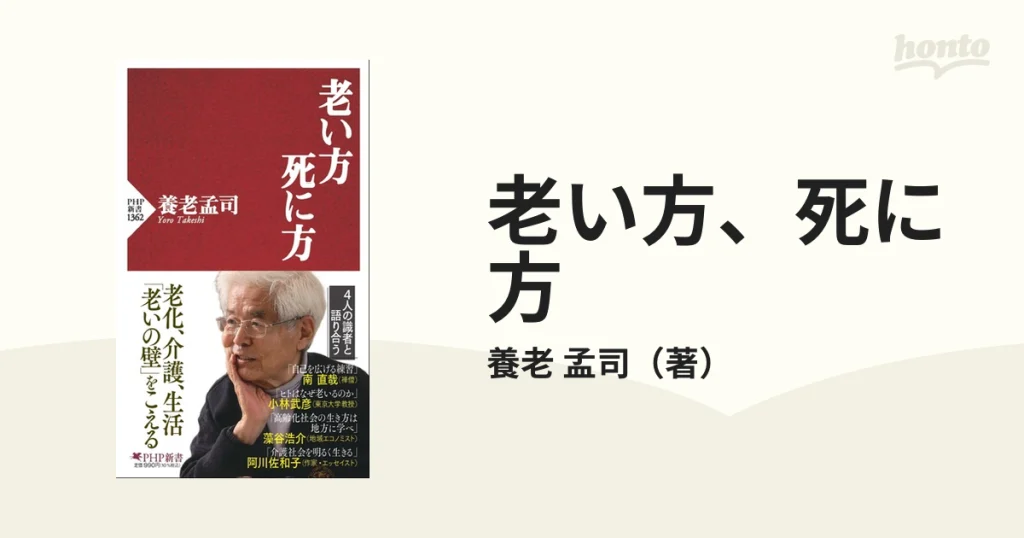
これがあるから、年寄りのほうは家族に迷惑をかけたくなくなる。それでボケを心配したり、なかには自殺してしまう人もいるのでしょう。
自分自身の状態を鑑みて、家族に負担をかけまいと死ぬ。『楢山節考』の世界そのままです。」(p169-171)
客観的基準で、社会全体で対応すべき

【養老】「安楽死や脳死ではなく、本来は、こういうところでこそルールを明文化して客観的基準を作ったほうが有効なのです。
こういう状態の障害ならばこのくらいの介護が必要であろう、そしてそれは家族では出来ないだろう、といった基準です。
その基準をみんなが了解していれば、『うちのばあさん、これじゃあとても家族じゃ面倒見切れないんですよ。誰か手伝ってください』という話が出来るはずです。
ところが、今はそれが非常にやりづらい。結局、家族内部の問題になると、日本人は非常に人目を気にする。だから家族で背負おうとして苦労をする。
本来ならば、『家族みたいな素人に介護させるなんてとんでもない』という考え方のほうが機能的だと考えてもいいのではないでしょうか。」(同p169-171)
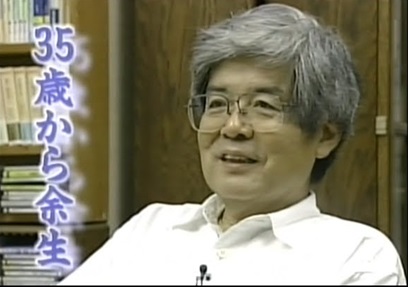
SNSで知り合いになった方で父親を自宅で介護されている方がいる。その方も「介護はやはり家庭ではなく専門スタッフに任せるべきだ」という話をされ、第三者にはわからないご苦労が伺える。
養老先生は、介護の問題はその場しのぎの小手先ではなく、国家の問題として政府がしっかりと陣頭指揮を執り社会全体で対応すべき課題だと指摘されている。
養老先生曰く、「昔は15歳で嫁に行ったから、30歳で孫が出来る。すると35歳過ぎたら余生だった。」
悩むのは当たり前
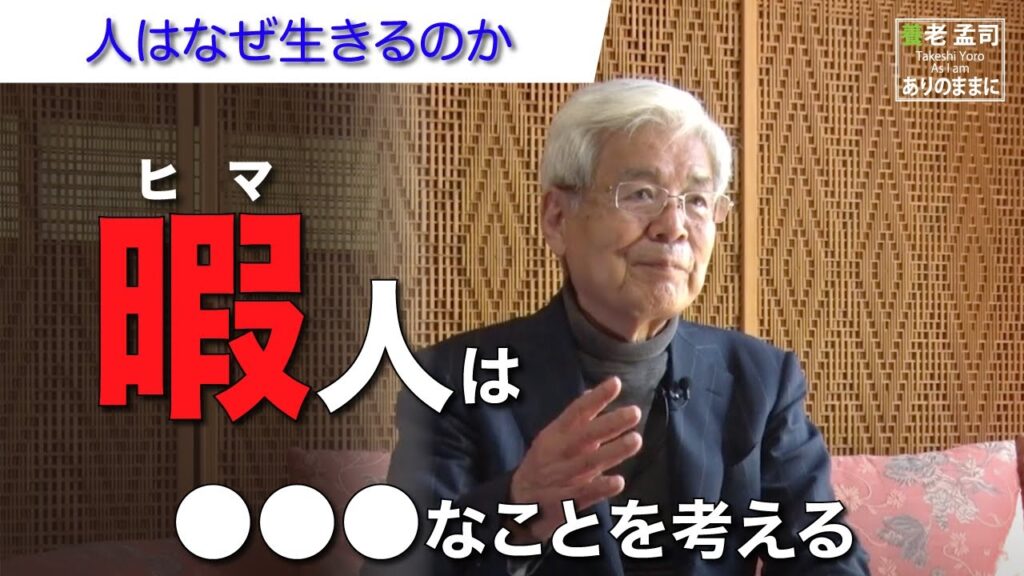
生きがいとは暇の産物
「生きがいとは何か」について、「かつては宗教家が役割を担っていたもの」と断った上で、養老先生は、次の様に解説している。
【養老】「生きがいとは何か」というような問いは、極端に言えば暇の産物なのだ、と。本当に大変なとき、喰うに困っているときには考えないことです。
喰うに困っていなくても、トイレに行きたくて切羽詰っているときには考えない。とにかく早く行って、出すものを出したいと思うだけです。
そのあとにホッとしてからじゃないと、生きがいについてなんて考える暇もないでしょう。
つまり何かに本気になって集中しているときには、生きがいとは何かなんてことについて考える余裕も必要もありません。
そういう人生論が求められるという状況は、現代人が感じている閉塞感が関係しているのでしょう。しかしそもそも人間、悩むのが当たり前なのです。」(同 p172)
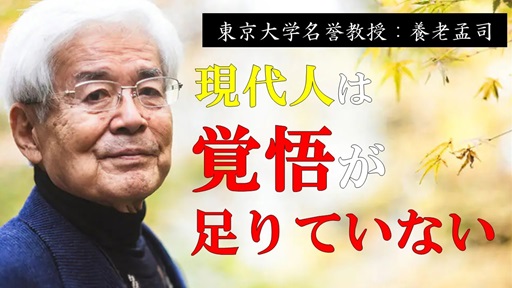
慌てるな
【養老】「自殺がいけないという理由は、大きく分けて二つあります。一つは自殺は殺人の一種であるということ。だから『なぜ人を殺してはいけないのか』というのと同じ理由です。
もう一つは自殺がやはり、周囲の人に大きな影響を与えてしまうということです。「二人称の死」なのですから。
私は自殺したいと思ったことはありません。簡単に言えば、「どうせ死ぬんだから慌てるんじゃねえ」というのが私の結論です。
こういうと『どうせ死ぬんだから今死んでもいいじゃないか』というやつがいるかもしれませんが、それは論理として成立していない。
なぜなら、それは『どうせ腹が減るのだから食うのをやめよう』『どうせ汚れるから掃除しない』というのと同じことだからです。
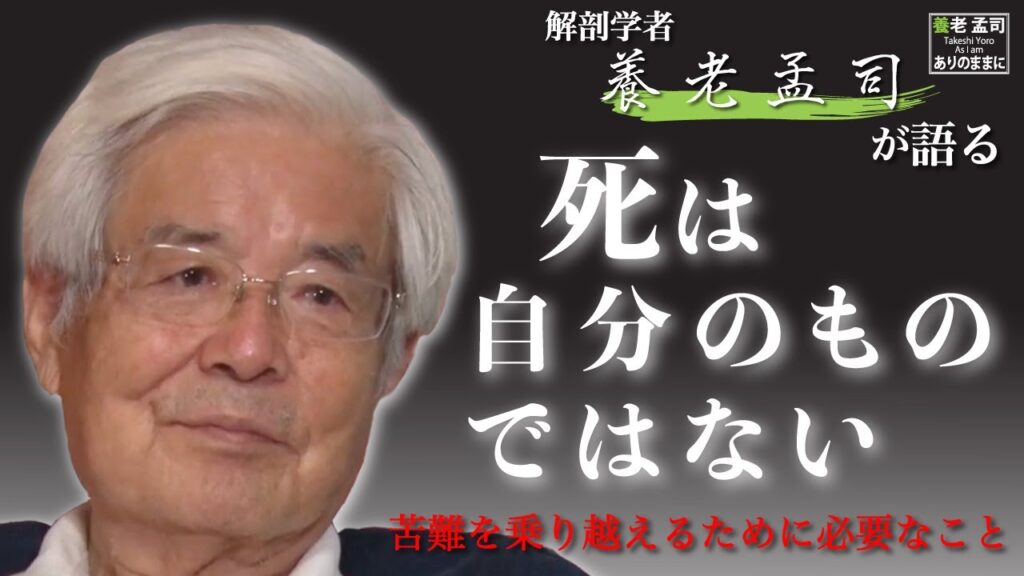
勝手に『一人称の死』についてのみ考えて、それが『二人称の死』としてどう受け止められるか、その影響を考えずに自殺することが良いとは思えないのです。」(死の壁p18)
なぜ人を殺してはいけないか
殺すのは簡単
【養老】「人は青酸カリで殺すことが出来ます。出刃包丁で殺すことも出来ます。『吸血鬼』に 出てくるみたいに、木の杭のような原始的な道具だって上手に心臓にぶち込めば殺すことが出来るわけです。
簡単に人間を殺すことが出来るこの青酸カリや出刃包丁や木の杭といったものが、人間とくらべたらどれだけ単純なつくりのものか。 システム(人間も含む自然や環境のこと)というのは非常に高度な仕組みになっている一方で、要領よくやれば、きわめて簡単に壊したり、殺したりすることが出来るのです。
だからこそ仏教では『生きているものを殺してはいけない』ということになるのです。殺すのは極めて単純な作業です。システムを壊すのはきわめて簡単。でも、そのシステムを「お前作ってみろ」と言われた瞬間に、まったく手も足も出ないということがわかるはずです。」(同p18)
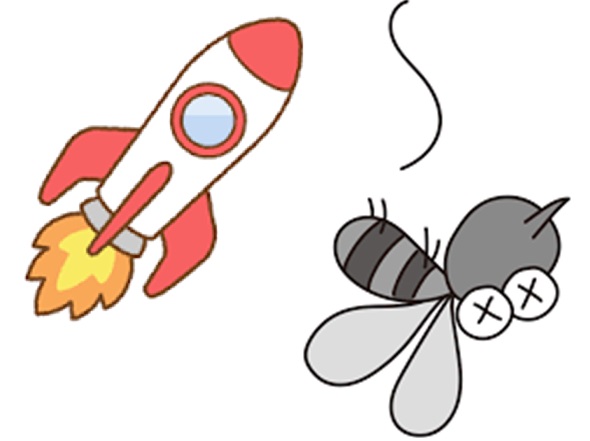
養老先生は中国までが月にロケットを飛ばす時代になったことを例に、ロケットは壊れてもまた作り直すことが出来るが、同じように飛ぶ蚊やハエは壊してしまったら二度と作れない、そして、「中国ほどの伝統のある古い国ならば、『うちはアメリカやロシアみたいに、ロケットなんてつまらないものは飛ばしません』くらいのことを言えなかったものでしょうか」と指摘している。
あともどり出来ない
人間を自然として考えてみる。
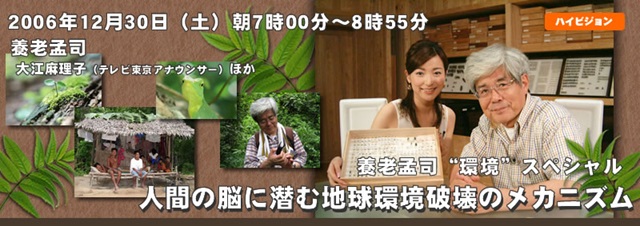
【養老】「つまり高度なシステムとして人間をとらえてみた場合、それに対しては畏怖の念を持つべきなのです。それは結局、自分を尊重していることにもなるのですから。
他人という取り返しのつかないシステムを壊すということは、実はとりもなおさず自分も所属しているシステムの周辺を壊しているということなのです。
『他人ならば壊してもいい』と身勝手な勘違いをする人は、どこかで自分が自然というシステムの一部とは別物である、と考えているのです。」(同p23)
「人間中心主義」は危険だ
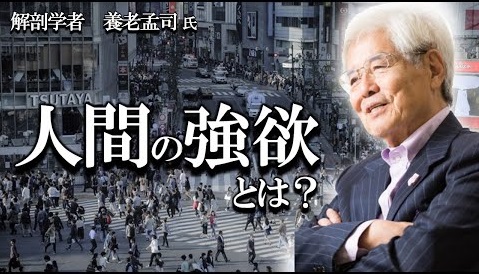
人間中心主義は神と自分という西洋思想
【養老】「それは実態としての人間の持つ複雑さとかそういうものとは別に、勝手に意識だけが人間のすべてだと考えるようになったということです。そして、自分の思い通りになることが一番価値のあることだという思想を、西洋近代文明は押し通してきた。
でもそれはおかしな話なのです。自分自身すら思い通りにならないことに気づけば、嫌というほど変わることなのです。」(同p24)
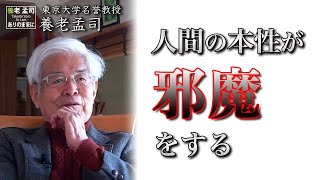
最後に釈尊のことばをご紹介したい。
すべての人々は生を愛し、死をおそれ、安楽を欲している、だから自己に思いくらべて他人を殺してはならぬ、また殺さしめてはならぬかれらもわたくしと同様であり、わたくしもかれらと同様であると思って、わが身に引きくらべて、(生きものを)殺してはならぬ。また他人をして殺させてはならぬ。(中村元 文庫本『ブッダのことば』p705)