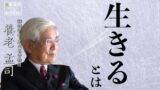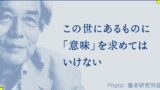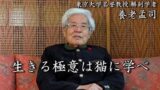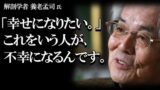⑮ 良き夫とは妻を尊敬している

【中村】「夫婦の間にはそれぞれ異なった義務があり、具体的に夫は妻に対してどうあるべきか、妻は夫に対していかなる義務を守るべきか、それを『シンガーラ青年への教え』という経典では五つの箇条にまとめて述べています。夫は次の五つの仕方で、妻に奉仕すべきであるというのです。ここで興味深いことは、妻に対して「奉仕すべきである」とか「敬うべきである」とか、そういうことばが使われていることです。」(中村元/原始仏典を読むp307)
第一に、尊敬すること。つまり夫は妻を尊敬しなければならない。
妻に対してさえ、神々に対するのと同じ尊敬をもってせよと言っており、カースト制の当時としてはずいぶん思い切ったことばだといえる。
第二に、しないこと。妻を軽蔑しないということ。
妻に 対しても礼儀がなければならないとのこと。
第三に、道を踏みはずさないこと。
これは主として男女関係に関することで、姦淫をも含めて、男の心が他の女性に移るのを戒めている。
妻以外の婦人と歩き回ることも悪徳と解されているそうだ。
第四に、権威を与えること。

これは家庭のことは妻にまかせるという意味。
中村先生は、「お前の気に入るようにせよ。といって食事と家事とをまかせてしまって、全権をゆだねるようにしなさいと言っています。そして、 妻にまかせてしまったら、やたらに干渉しないのがよいのです。夫は社会に出て活動するものですから、家庭内の事柄に一々気を使うのは、それだけ社会的活動の力をそぐことになる。家庭のことは妻に権威を与えてまかせてしまうならば、夫は外で働いている間、気を使わないですね。それで夫として社会的なつとめを思うままに関すことができるのです。当時のインドでは『妻は常に夫なる主人を畏れる』という状態で、『常に自在(主権支配権のあること)であることができない』と嘆かれておりましたので、それを是正するように説いているのです。」
これは日本でも昭和時代まではこの戒めは的を射ていたが、昨今の共働きをしないと生活が出来ない現状を考えるとここの捉え方はそれぞれの置かれた状況で読まなければならないと考える。
第五に、妻に装飾品を提供すること。

つまり、お化粧品や装身具を買ってあげなさいということ。
ただし、自己の財力に応じて装飾品を提供することだとも書かれている様だ。
これらのことに関して、中村先生は、「これは反面、初期の仏教においては在俗の婦人の好みに対して温かい同情をもっていたことを示しています。また経済的観点から見ると、必ずしも贅沢を勧めたことにはならないのです。南アジアの婦人たちにとっては、貴金属の装飾品は一種の銀行預金としての機能をもっております。お金がたまると装飾品をふやし。お金が必要になると少しずつ売却する。ですから装飾品を買い与えることは、銀行預金をふやすのと同じことになるのです。」
この解説をもう少し補足しておくと、現在もインド人女性は体中に宝石を纏っているイメージがあるが、これはお金なら王朝が変われば使い物にならなくなる、陸続きなのでいつ異民族が攻めて来て王朝が滅びるかわからない。
世界中でもクーデターなどで政権交代しお金の価値が突然紙くず同様になってしまう事例はたくさんあることからも言える。家という財産も火災にあえば失ってしまう。
だから、宝石にして身につけておけば災禍の時に逃げてその宝石を売ってお金に出来るだろうという釈尊の画期的な考えが今も引き継がれているからだとされる。
「世界で最初に女性の自立と財産権を認めたのは釈尊だ」と植木雅俊先生は述べている。
(YouTube動画 池田香代子の世界を変える100人の働き/原始仏教・大乗仏教の溌剌とした女性たち)
男性が女性に奉仕しなさいというこれらの教えは、中国で漢訳された際に全て真逆に訳されて日本に伝わっていることも理解されたい。
夫婦は直角に向かい合うのが正しい/養老孟司
養老孟司先生の後援会動画の中に、夫婦について語っている部分があるので引用したい。
【養老】「よく夫婦の話でもするんですけども、結婚したては、相手が気に入らないとか見えてきますからそれを直そうとするわけです。直そうとするとどうなるかというと大ゲンカになっていくんですね。
私もだいぶそれをやってですね。
私もそういう時は必ず最後は先ほど申し上げましたような損得勘定に直すことにしてます。
考えてみるとこうやって女房を直そうと思ってしょっちゅうケンカしてたらですね、全然割があわない。一文(いちもん)にもならない。
考えて見たら「気に入らないと思っている自分」の方を変えるのは タダじゃないか!って結論が出てくる。
自分の方を変えてしまうとどうなるかというとですね、一文もかからないんですわ。それで家庭が平和になります。これは丸儲けで、さらに考えると、自分の好みも変えられないようで相手を変えようっていうのは僭越な話ですわな。」【公式YouTube 養老孟司/【養老孟司】不安から逃げていませんか?】
夫婦は向かい合わないほうがいい
そして、「養老訓」には、『夫婦は向かい合わないほうがいい』とあるのでこれも掲載する。
「『夫婦は直角に向かい合うのが正しい』と私はいつも言っているのです。
夫婦といえども、価値観や考え方は異なる。正面から向かい合うと、ぶつかる危険性がある。
直角はなぜいいか。夫婦は二人で暮らすのだから、外から見ると、必ず合力になります。二つのベクトルが直角になっているときに、力はいちばん大きくなります。
いちばん無駄なのは、お互いが向いている方向が正反対なときです。
まったく同じ向きはどうでしょう。これは良いようで、そうでもない。実は長いほうで済んでしまう。力はなかなか足せないので、長いほうだけあればいい。
夫婦に限らず、人間が共同して作業するときはできるだけ直角になるようにすることです。」
『夫婦は向かい合わないほうがいい』