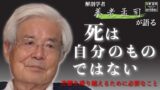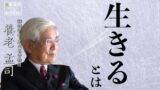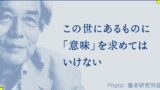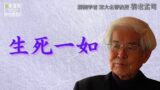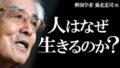㊶飛び降り自殺をする人が絶えない
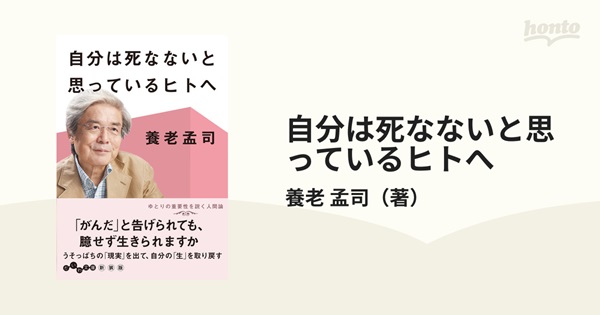
過去に死ななかった人はいない
【養老】「これだけは間違いない。過去に死ななかった人はいません。人生の最終解答は『死ぬこと』だということです。私がまだ東大の解剖教室にいた頃の話です。
自殺の名所といわれる団地が都内にありました。そこに解剖のためのご遺体を引き取りに行ったことがあった。生前に献体に同意された方の遺体を私たちは解剖に使わせていただきます。そういう方が亡くなったとなると、私が遺体を引き取りに伺うのです。
亡くなった方は団地の十二階に住んでいました。ご遺体の入った棺を持って通路を進んでいくと、その団地のドアは外開きだから住民がドアを開けるたびに遮られる。向こうはこっちを見て慌ててドアを閉める。
そんなふうに進んで、いざ棺をエレベーターに載せようとしたら、横にしたままで入りきらない。もっと低層の建物ならば棺を持って階段で降りることもできるでしょう、十二階ともなると大変です。
仕方が無いから、生きているとき同様に、立ってエレベーターに乗っていただくことにしました。棺を垂直に立てて載せて運んだのです。
このときに、ここは人が死ぬことを考慮していない建物だと思いました。
死を想定していない若い人向けの団地

その後、実際にその団地を設計した人と話す機会がたまたまあり、そこで、この話しました。
すると彼は、『あそこは若い夫婦が郊外に一戸建てを買うまでに住むところという想定で作ったのです。ある程度そこに住んでお金が溜まったら出て行くのです。』と言う。
やはり、設計者はそこで人が死ぬということを想定していなかったのです。
しかし、いくら若夫婦が住むといっても、何千人も住む団地で人が死なないはずはありません。
にもかかわらず、死を想定していない。これはまさに都市化の象徴ではないでしょうか。ここでいう都市とは自然の対義語として使っています。
都市はそういう自然を排除していくことで作り上げられました。人間の脳が考えたものが形となって現れたのが都市です。
飛び降り自殺が絶えない

そこでわざわざ飛び降り自殺をする人が絶えないというのは、一種の復讐のような行為と解釈することが出来ないでしょうか。『一体、なんておかしなものを作ってくれたんだ』ということなのです。
現代人は往々にして死の問題を考えないようにしがちです。しかし、それは生きていくうえでは決して避けられない問題なのです。」(養老孟司:死の壁/最終回答p13-15)
この団地は自殺の名所として有名で、上京しすぐに聞かされた時は不気味なところがあるものだと思ったものだ。
病院ですら死体は忌み嫌われる

病院ですら死体は忌み嫌われると養老先生は講演会で次の様な話をされている。
【養老】「解剖させていただく方は生前約束してあり、亡くなったらいつでも引き取りに伺う。元旦の時もありました。埼玉県の病院で、婦長さんがあわてて『元旦に最初にエレベーターを降りてきたのが死人では病院では具合が悪い』という。」
都市は人が死ぬことを想定していない

この話を読んで、いろいろと思い出すことになった。
戸建てに居た頃は、私の住む閑静な住宅街は道路を挟んで団地が立ち並ぶエリアだった。
ある日保護した仔猫(三毛猫師匠)の体が弱く、その子に合う獣医を探す毎日であちこち駆けずり回っていたが、どこの獣医もペットなんでも屋で、どうも力が入っておらず猫さまとも相性が悪く体調も改善されない。
ようやく巡り合ったのが今の獣医なのだが、自宅からかなり離れておりどうするか考えた末に猫を優先し自宅を処分することにした。
独りになって戸建ては建物も庭も手入れが大変だったので決心は早かった。
余談だが、自宅にはホームエレベーターをつけていた。ホームエレベーターは基本二人乗り設計だから車いすの方だとそれだけでいっぱいになる。もし人が二階で倒れたら救急隊員はストレッチャーで階段を降りなければならず戸建ては階段のつくりによってはこれまた至難の業になる。
売り出しするとすぐに希望者があり内見に来られたのは隣の団地群に住む若夫婦だった。
エレベータがある棟とない棟があるらしく、その夫婦は若いからとエレベーターの無い四階建ての最上階があたったようだ。一階は全て高齢者や体に障害を持つ方に優先的に割り当てられているという。
聞くところによるとその団地もエレベーターがある棟は4~5人乗ればいっぱいになる広さのものがついているだけだと言っていた。
その夫婦のように戸建てに住むまでのつなぎとして住んでいる若夫婦がほとんどだから、そこもまた人が死ぬことを想定していない団地なのだろう。
昔から、団地の一階は高齢者や障害を持つ人に優先的に割り振られて来た。表向きは利便性というがそれなら手すりやスロープがあっても良いがそんなものはなかった。
つまり、ホンネのところは運び出す際に大変だからではないのだろうか?
マンションは高齢者を避ける

今のマンションが新築だったので完成までの間、仮住まいしたマンションも分譲にもかかわらずやはりエレベーターが狭いのだ。
戸建てからの引っ越しだったので、地下にあるトランクルームに荷物を運ぼうとしてもエレベーターが狭いのでなんども往復になった。
現在のマンションも同程度の広さなので何かあっても救急隊のストレッチャーをそのまま入れることは出来ない。やはりここもまた病人や死人が出る想定になっていないようだ。
確かに間取りも様々で、単身者や若夫婦も多く私の年齢は上の方ではある。
タワーマンションも病人や死人を想定していない
二年ほど前、近くにツインタワーマンションが出来てからは冬季間の日中は二時間ほど太陽が遮られるのと、タワーマンション特有のビル風が強く行き交う人は歩くのに難儀しており帽子を飛ばされるなど苦労されている。

このタワーマンションもまた若夫婦ばかり住んでいるのだが、先日そのことをSNSで投稿してみた。
私は仕事柄、情報収集のために世間の反応を確かめる時にSNSで投げかけるのだが、想定通りの反応がたくさんあった。
やはり反応された方々は自分は死なないと思っているのだろう。タワーマンションを買った若夫婦に対するコメントばかりだ。なぜ、若夫婦ばかりなのか?という疑問は湧かないようだ。
ある日、そのタワーマンションに入ろうとしてベビーカーをドアに挟んで困っている方がいたので、助けてあげたついでに設備などを聞いてみた。
やはり、そのタワーマンションもエレベーターは狭いのだといい、ベビーカー利用者が複数で乗るのは大変だと言う。
人が死ぬことを想定していないから若夫婦を中心に販売しているのだろう。
高齢者こそ便利な暮らしをすべきだが・・・

私は高齢になるほど駅に近い便利な立地の暖かいマンションに住むべきだと考えるが、現実はいくら金があってもマンション入居は断られるからアパートに住むしかなくなって来ている。
駅近くの便利なところにはアパートはまずないから少し離れた場所になり高齢者にはかなりの負担だろう。

いまや街中の公共施設、ホテル、ビルのエレベーターも地下鉄のホームとの連絡エレベーターも広い設備に出くわすことはまずない。
人が死ぬことを想定していない世の中になってしまった。
みなさんの周りの設備も一度点検して見られると人が死なない地域に住んでいることに驚くのではないだろうか。
救急搬送や死は老若男女を問わないと思うのだが…
エレベーターの定員数は、一般的に、その積載量を一人あたりの体重で割った値によって決まるとされ、その基準となる体重は? 社団法人日本エレベーター協会によれば、日本のエレベーターは一人あたりの体重を65キロと設定し、定員を決めているという。だから一定数乗ればブーと鳴った経験があるかと思う。
つまり、重さが基準であり奥行ではないのだ。