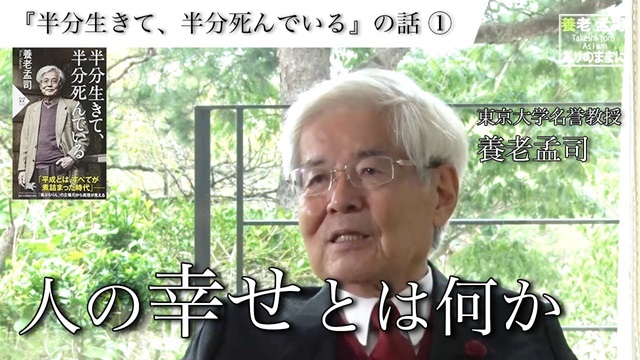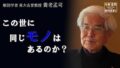⑫ こよなき幸せ-スッタニパータ
人生の幸福とは何であるか?
「スッタニパータ」という釈尊の教えを集めた原始仏典には、「こよなき幸せ」という一節で根本の原則が纏められており、その中から現代の我々が参考とすべきものを紹介したい。

<こよなき幸せ>
<こよなき幸せ>(中村元/原始仏典を読むp294-300)
●諸々の愚者に親しまないで、諸々の賢者に親しみ、尊敬すべき人々を尊敬すること。
ここでいう「愚者」とは人間としての道理に気づかない人を指し、道理を知って体得している人が賢者とされる。
例えば、金儲けが上手くさらに自分の財産を増やそうと汲々とし夜も安眠できないような人は、いくら頭がよくても愚者であると中村先生は解説している。逆に、知識に乏しく計算や才覚が下手でも、心の安住している人は賢者だとする。
●適当な場所に住み、あらかじめ功徳(よい行い)を積んでいて、みずからは正しい誓願を起していること。
この句は、当時の修行者向けに書かれているので、現代の我々向けとしては、養老孟司先生が一般社団法人YORUMORI/YouTube動画「森とは何か」でコメントされているので紹介したい。
“現代人は怠けることに誠心誠意”

『都会は自然を排除する』こんな言い方を僕はしていますが、都会はすべて意識的に物事を判断しようとしています。その結果、都会と自然のバランスが失われ始めました。昼でも夜でも一定の温度と明るさが保たれた室内で過ごし、デコボコのない真っ平らな道を歩く。
合う人には合うかもしれませんが、全員が全員合うわけがない。人はそれぞれ違って当然なんですから。
要するに現代人は一定の刺激しか受けなくなってしまったんです。それを便利とか快適とか言っている。ある意味でこれは怠けですよ。現代人は誠心誠意怠けることに力を注いできたということです。」
“現代人は自分の体のことが分からなくなっている”
「僕は、森が良いから『森へ行け』って言っているわけではありません。
結局は自分自身のバランスの問題なんです。現代人はすべてのことを頭で考えて自分たちにとって便利で快適な環境をつくってきたわけですが、脳はもともと自分の体のことを考えるようにはできていないんですよ。
脳は外側の世界をどうこうするもので、内側の世界にはまったく無頓着。だから体の中に癌が潜んでいても分からないんです。
しかし本来、生き物は自分の体のことをある程度は分かっていていいはず。自分がどうすれば元気になるのか、多くの人が忘れてしまっているんですね。」

虫の声すら聴き分けられない現代人
現代社会の暮らしは、特に都市部でアスファルトが土を全て覆ってしまい、公園も草木も意味を持って植えられており、建物含め全て人工物の中で暮らしバーチャルを当たり前の様に取り入れている。
リゾート施設も自然ではなく人工的に作られたものを指すようになっている。
特に、今の若い世代は生まれた時から便利な人工物の中で暮らしており、ゲームなどのバーチャルに浸る生活が当たり前になっているため、虫の声すら聴き分けられない若者が増えているという。
都市部では子供の声が騒音問題になっているが、これは都市部の子供が異常なまでの奇声をあげるからで、地方の子供を含めた子供が全てそうだという話ではない。
奇声をあげる子供はその親も奇声をあげていることが多いとされ、ゲームやコンピュータのバーチャル音が影響しているようだ。
SNS利用者同士の人間関係で自殺する人もいる昨今だが、あくまでSNSはバーチャルであって、これからは相手がAIかも知れないと理解して使わないとAIの言葉に傷ついて自殺する人も出て来るだろう。
人間の体は自然だが、西洋思想を取り入れた日本人はいつしか一神教の「人間は神が作ったもの」の影響を受けて本来の自然である体を忘れ、さらには自然に回帰するどころか逆に母なる自然を嫌い排除するようになっているのが人工物だらけの都市を見ればわかるはずだ。

養老孟司先生は、都会と田舎のちょうどバランスのとれたところがあるはずだと指摘し参勤交代(都会と田舎の往復生活)の必要性を提唱されている。
先日、テレビの情報番組で紹介された都内に住む若いご夫婦は、週末は子供二人を連れて、親元の田舎に帰ると話されていた。
何故、そんな生活をするのか?との質問に「特に理由はありませんが、子供たちも喜んでいるのでいいかなと思っています。」と答えられていた。
この若いご夫婦は、養老先生の唯脳論をご存じかどうかわからないが、人間の脳が創り出した人工物だらけの生活から離れることの大切さを感じ取り、週末の田舎暮らしをされているのではないだろうか。これこそ、「正しい誓願を起している」ことだと思う。
●深い学識あり。技術を身につけ、身をつつしむことをよく学び、ことばがみごとであること。
これはまず社会の変化に対応するためにアンテナを張り巡らし正しく敏感であることだと考える。
現実は目まぐるしく変化している毎日にも拘わらず、ぼんやり暮していているのが現代日本人かも知れない。これを平和ボケだと揶揄されることもある。
IT社会の現代ではそれに振り回されても良くないが、少なくとも最低限の新しい知識(情報)を得るよう心がけ使いこなせるよう自己を訓練し、向上に努めるべきだといっているのだろう。
そして、『ことばがみごとであること』というのは、きちんと自分の考えを意見として口にすることを言うのだろう。この態度は仏教では常に尊ばれたとされるが、現代の日本人はみんな一緒を好むので周りを見て言動をしているのも事実だ。
●父母につかえること、妻子を愛し護ること、仕事に秩序あり混乱せぬこと。
「家庭の幸福はもっとも身近な幸福であります。それは降って湧いてくる幸福ではなくて、育てはぐくむことによって現れてくるものです。また、『仕事に秩序あり混乱せぬこと』というのは、職業人にとって本質的なことです。」と中村元先生は解説されている。
「仕事に秩序あり混乱せぬこと」とは、IT、AI化の現代社会においては、この教えの必要性を痛切に感じる。
特に、昨今の利益至上主義から企業の不正が相次いで発覚している事例をみれば一目瞭然だ。
働く側にすれば、生活の軸であり生きる糧でもある仕事を毎日狂いなく行なうことが大切だが、それによる生きがいを感じることも欠くことができないだろう。
ただ、この生きがいを「自分に合ってる仕事」だと勘違いしている昨今の若者も多い。
養老孟司先生は、「超バカの壁」の中で、
「仕事というのは、社会に空いた穴です。道に穴が空いていた。そのまま放っておくとみんなが転んで困るから、そこを埋めてみる。ともかく目の前の穴を埋める。それが仕事というものであって、自分に合った穴が空いているはずだなんて、ふざけたことを考えるんじゃない、と言いたくなります。」と指摘している。そして、「仕事は自分に合っていなくて当たり前です。」と厳しく戒めている。
つまり、仕事の生きがいとは、自分に合った仕事をするのではなく、それをやることで社会や他者のためになることで生きがいを感じられることではないだろうか。

●施与と、理にかなった行ないと、親族を愛し護ることと、非難を受けない行為
「『施与』というのは贈与と言いかえてもけっこうです。物質的なものであってもよいし、精神的、無形のものであってもかまいませんが、他の人々に何ものかを与えることによって、人々を助けることができるのです。
『自分だけのものだ』と独り占めするのではなく、他人に何かを与えるところに人生の深い喜びがあるのではないでしょうか。」と中村元先生は解説されている。
●悪をやめ、悪を離れ、飲酒をつつしみ、徳行をゆるがせにしないこと。
酒で人生を狂わしてしまった事例は昔も今も変わらないこということではないだろうか。
●尊敬と謙遜と満足と感謝と(適当な)時に教えを聞くこと。
●耐え忍ぶこと。ことばのやさしいこと、諸々の(道の人)に会うこと、適当な時に理法についての教えを聞くこと。
「『満足』とは、人は大きな志を立てると、くだらぬことで不満を訴えることはなくなってしまいます。
『感謝』 というのは、お互いに精神的な喜びを与えあうものです。どこの国の人にもこの気持は共通で、日本人は『ありがとう』と言い、朝鮮の人は『カムサ』と言う。これは「感謝」の発音を写したものです。ベトナムの人は「カンノン」と言うが、これも「感恩」の音を写して言うのです。
次に、「適当な時に理法についての教えを聞く」というのは、適当な時に仏教の教えを聞くという意味です。
古代のインド人や現代の南アジアの人々は、陰暦の半月の第八日および第十五日に寺院に参詣して教えを聞きますが、そのようなことを言ったのです。」と中村元先生は解説され、正しい教えを率先して学ぶことの大切さを教えられている。
●世俗のことがらに触れても、その人の心が動揺せず、憂いなく、汚れを離れ、安穏であること。
「世俗のことがらに触れてもその人の心が動揺せず」ということは、 志を固くもって誘惑に負けないことであります。」と中村元先生は解説されている。
釈尊の幸福に喜び満ちあふれている心境が感じられる句であるが、現代の我々にとっての教えでもあり、その、目ざすところは、あらゆる生きとし生ける者どもが幸せであれ、ということになる。

目に見えるものでも、見えないものでも、遠くに住むものでも、近くに住むものでも、すでに生れたものでも、これから生れようと欲するものでも、一切の生きとし生けるものは、幸せであれ。
そして、この句の最後を次のことばで括っている。
●これらのことを行なうならば、いかなることに関しても敗れることがない。あらゆることについて幸福に達する。―これがかれらにとってことなき幸せである。(中村元/文庫本『ブッダのことば』p258-69)
今回は、「人生の幸福」について仏典にある根本原則を纏てみた。
次回は根本原則が人間の生活の中に具体的にどう生かされるのか、引き続き仏典解説を見ていきたい。