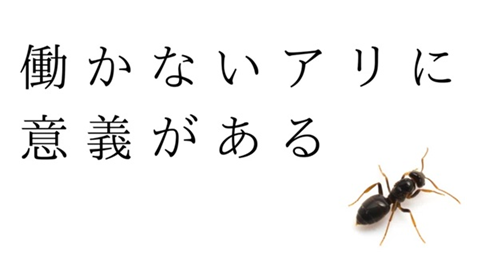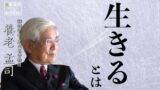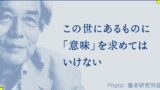⑲ 雇用主は使用人に奉仕しなさいと釈尊は説いた
使用人に奉仕する
雇用者と使用人、企業を経営している人がいるとすれば、使われている人がいる、その両者の関係についても釈尊は説いているので、中村元先生の解説を見てみたい。
中村「『シンガーラ青年への教え』では、両者との関係を相互的な義務の関係としてとらえているのであります。
主人は次の五つの仕方で奉仕しなければならない。「奉仕する」ということばが使ってあるのです。
第一に、その能力に応じて仕事をあてがうこと。
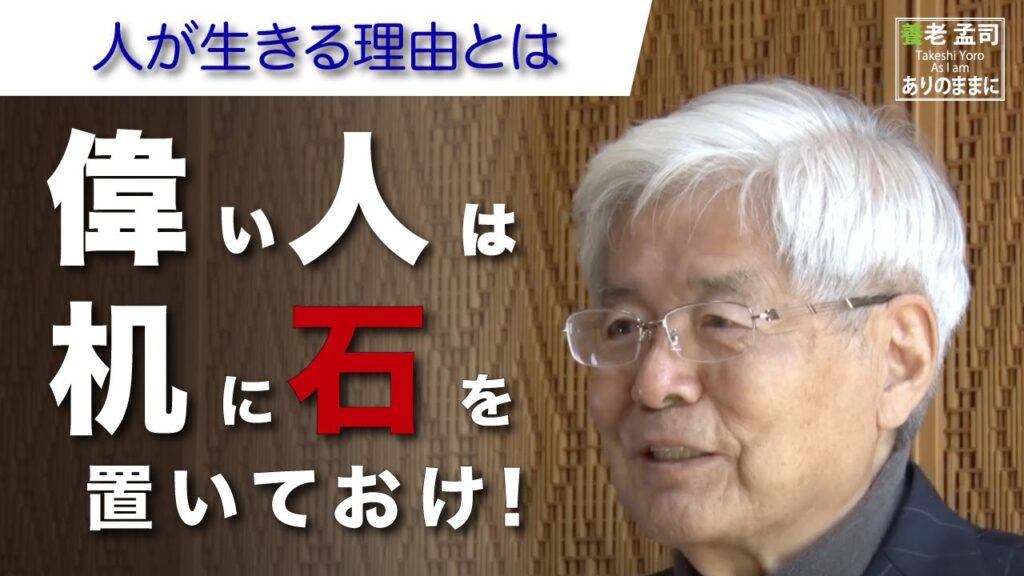
注釈書によれば『若者のすべきことを老人にはさせず、老人のすべきことを若者にはさせず、女のすべきことを男にはさせず、男のすべきことを女にはさせず、それぞれの力に応じて仕事をあてがう』と、ここでは労務を適当に配分すべきことを説いています。
例えば未成年の少年少女に過重の労役を課すということは、古来どこの国でも行なわれてきたことですが、これを戒めているので、老人中婦女の労働に対する労りということも大切です。
第二に、食物と給料とを給与すること。
『この男は少年である、この男は独身者である、というように、その人に適当な程度を顧慮して食物を与え、費用を与える』と いうことです。
つまり年齢差や家族手当の問題に相当することを述べているわけです。
仏教は一面では非常に現実的な面もありました。
「生きとし生ける者は食をもととしている」ということは、仏典の中にしばしば説かれていることです。食物の問題の解決が生活の基礎になることを見抜いているのです。
※ちなみに、戦争とはこの食物の奪い合いから始まっている。
第三に、病時に看病すること。
つまり「健康でない時には仕事をさせないで、快適な物品・薬品などを与えて看病すること」です。当時としては、大変に使用人を思いやったことばといえるでしょう。(現代の福利厚生的)
第四に、すばらしいご馳走のあった場合には分ち与えること。
これは「珍しい甘味を得たならば、自分では食べないでも、かれらのためにも、その中から分ち与えること」です。
自分は食べないでも、使用人にまず美味を与えるということは、なかなかできないことです。しかし、もしこれができたならば、労使の間の感情的な差は起きないでしょう。
第五に、適当なときに休息させること。
これは注釈書によれば「常時にまた臨時に休息させることである。』とあります。
『常時に休息させる』とは、人々は一日中仕事をしているならば疲れてしまう。それゆえに、かれらが疲れないように。適当な時を知って休息させるのである。
『臨時に休息させる』とは、祭礼などに、装飾品・器・食物などを与えて休養させるのである」。
人間は、働き通しでは本当に能率をあげることができない。どうしても適当な休養をとることが必要である。」

働かないアリに存在意義がある
ここで、注目するのは第一に挙げている「その能力に応じて仕事をあてがうこと。」
昨今の日本社会は、効率主義、成果主義が当たり前の様に唱えられている。これは欧米のマネをしているに過ぎず、これで日本社会がおかしくなったのではないかと私は考えている。
面白い研究発表が注目を集めている。「働かないアリに存在意義がある」(長谷川英祐)
「働かないものに存在意義があるのか?」への超納得の回答――進化生物学者が教えてくれること
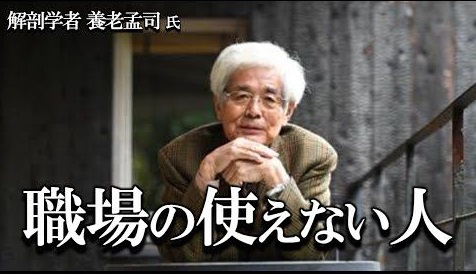
「アリは働き者だ」と言われているが、巣の中にはほとんど働かないアリが2~3割ぐらいいるのだという。「2:8の法則」と呼ぶそうだ。
「働かないアリ」というのは、いざという時のピンチヒッターみたいなもので、誰もその仕事をやれなくなった時に、ヘルプに入るそうだ。つまり、全部のアリが働いて疲れてしまったら代わりがいなくなる。
そこで、疲れたアリの代わりにヘルプに入るアリを用意しておく必要がある。そして全員が得をして存続していく「共生系」社会が大切だと結論付けている。
これに関して、養老孟司先生は、「働かい2割を取り除くと働くアリばかりになるかと言えば、また働かない2割が発生する。これを繰り返せばアリは絶滅する。人間社会も同じではないのか」と警鐘を鳴らされている。
成果主義、能力主義は釈尊の教えに反する
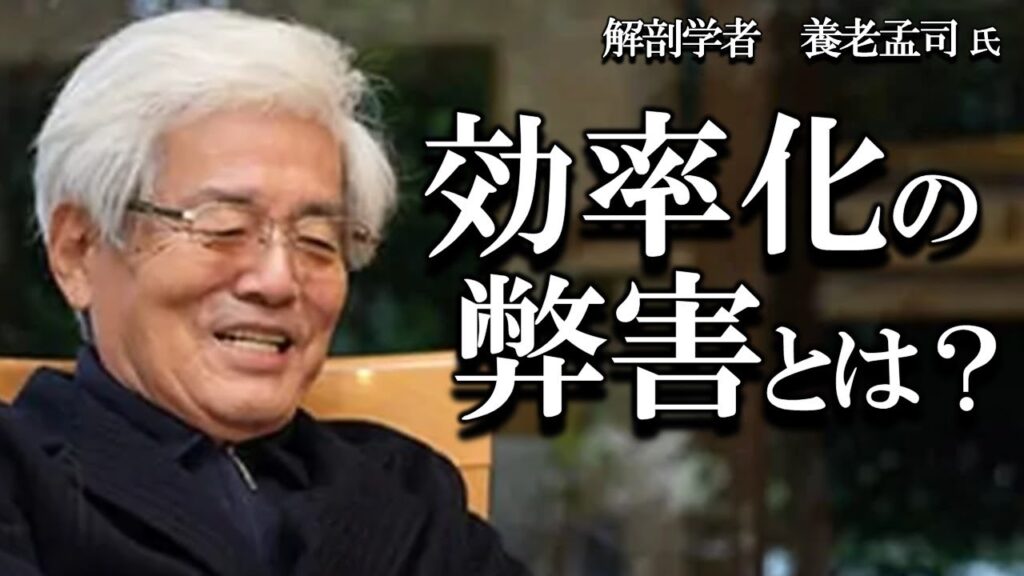
また、養老先生は、著書「逆さメガネ」の中で、日本という共同体におけるルールというか価値観と、アメリカやイギリス、フランス、ドイツでの共同体における価値観というのは微妙に異なると指摘している。
「これがバブル崩壊以降、ちょっとおかしくなった。おかしくなった社会はアメリカの猿真似をして「能力主義」『成果主義』を前面に出して共同体のルールの変更を試みたが、そんなもの上手くいくわけがない。
日本では今でも企業は一旦採用した社員を解雇することが難しい。どんなに無能でも、どんなにそいつが反社会的な反抗者でも、解雇することが原則出来ない社会である。アメリカのように、藪から棒に『キミを解雇する。15分以内に私物をまとめて出て行け」とは言えない社会である。
だから日本では能力主義、成果主義は基本的になじまないし根付かないのである。日本では社会の構成員を切り捨てず、なんとか騙し騙し使って、全体の平均的生産性を上げようとする社会なのだ。
フィンランドの教育がどうしたの、アメリカのボーディングスクールがどうしたのと騒ぐバカが巷に溢れているが、所詮、こいつらは日本社会の落ちこぼれであって、それが悔しくて、なんとか話を自分の都合の良い方向に誘導すべく海外の『自分に都合のよい事例』をそこだけ切り取って主張しているに過ぎない。要するに我田引水なのだ。
社会にとって最も大切なものは信頼であり、だからこそ社会を破壊しようとする不逞の輩は、社会の信頼関係を壊そうとしているだけだ。」
周利槃特への教え
釈尊の弟子の7番目に周利槃特(しゅりはんどく)という覚えの悪い弟子がいた。自分の名前すら忘れてしまうという。釈尊は毎日掃除の仕事をさせ『塵(ちり)を払い、垢を除かん』と唱えよ」と言った。
その通り続けて、周利槃特は覚りを得てブッダになったとされる。
西洋思想信仰をしている世の経営者諸氏は労働者を人間と見てはおらず必要に応じてスペアを交換すればよい的なモノ扱いをしている。ぜひ、このブログを読んで反省してもらいたいものだ。
次回は使用人(従業員)のつとめについて書きたい。
【追記参考】上司が部下に絶対してはいけない「2つの質問」とは
(ダイヤモンド・オンライン24/2/7号)