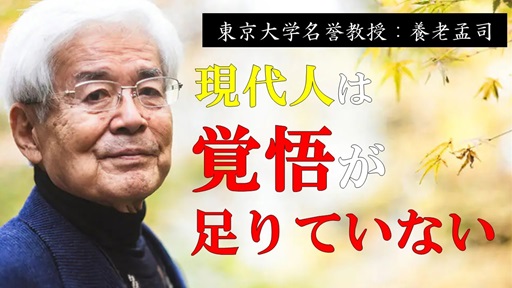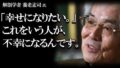㉒ 五つの戒め
一切の生きとし生けるもの幸いであれ。安穏であれ。安楽であれ。
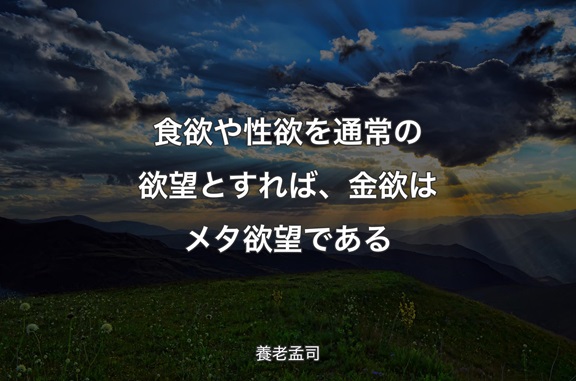
前稿までは、仏教が説く慈悲の理想として、人間はどう生きるべきか、について、夫婦、家族、労使、友人など身近な倫理について取り上げてきた。
今回は、さらに人間は単に家族などの共同体の成員でだけでなく、社会人として広く人々と付き合わなければならないことから人が社会人として行動するとき、どんな道徳を守らなければならないかについて、仏教では世間一般人がたもつべきものとして、五つの戒め「五成」があるので取り上げたい。
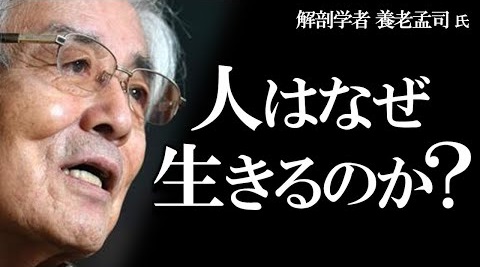
1.不殺生戒(ふせっしょう)
2.不偸盗戒(ふちゅうとう)
3.不邪淫戒(ふじゃいん)
4.不妄語戒(ふもうご)
5.不飲酒戒(ふおんじゅ)
1.不殺生戒

第一に、生きものを殺すなかれ。
すべての者は暴力におびえ、すべての者は死をおそれる。
すべての生きものにとって生命は愛しい。
己が身にひきくらべて、殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ。
ダンマパダ(中村元著『真理のことば』岩波書店)
仏教では、「生きとし生けるものに対して暴力を用いない」というのが、理想とされている。
仏教の説く不殺生は、人間を殺してはならぬということが第一だが、理想としてはすべての生きものを殺さぬことだとされる。
中村先生の解説では、
【中村】「なぜ生きものを殺してはならないかというと、いかなる生きものにとっても『自己よりもさらに愛しいもの』はどこにも存在しない、『同様に他の人々にもそれぞれ自己は愛しい。ゆえに自己を愛する者は他人を害してはならぬ』からである、と言われるのです。
ただ現実の問題になりますと、生命を奪うということを原始仏教の信徒でも行なっていました。実際には肉食、交戦、農業を認めていたわけですから、やはり問題は残されているのです。」(中村元/原始仏典を読むp331)
後世の我々に宿題を残した釈尊
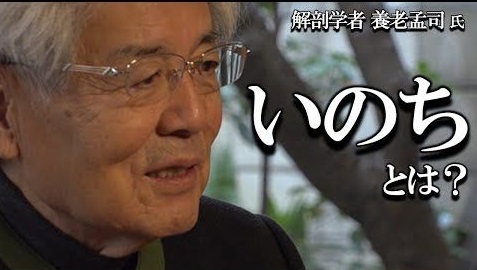
この殺生に関する倫理は、後世の我々の時代まで課題として解決されないまま残っているということになるのか…
これについて、日本仏教学院のHP/五戒とは?
「蚊やハエなどの虫も含めて、どんな生き物を殺しても、殺生罪となります。
さらに、自らの手で殺さなくても、人にお願いして殺してもらうのも、「他殺」という殺生罪となります。たとえば、スーパーで売っている魚を食べるのも、猟師の人に魚を殺してもらっていることになりますし、豚や鶏を食べるのも、畜産農家の方に、代わりに殺してもらっていることになりますので、殺生罪です。また、野菜を食べるときでも、農家の方に「害虫駆除」をしてもらっていますので、やはり殺生罪です。また、新幹線を使ったり、車でスピードを出すと、ライトのところに虫がぶつかって、たくさんこびりついて死んでしまいますので、やはり殺生罪です。」とある。
養老孟司先生は、自然界の有様を調べるのに長年にわたり虫を採取されているが、鎌倉市の建長寺に隈研吾氏が設計した虫塚を作り、毎年6月4日に虫供養を行っているという。
動画では、「供養に対して独特な文化を持つ日本だが、相手への祈りが(加害者としての)自分の心を鎮めている」と語っている。
【公式】養老孟司 供養とは自分の心を鎮めるもの 令和4年虫供養
2.不偸盗戒
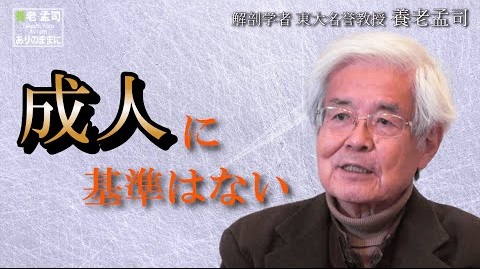
第二に、盗みをするなかれ。
人間はなんらかの意味において、道具や所有品なしには生きていけないのだから、他人の所有物を奪うことは非常な悪だとし、そこで「盗むことなかれ」ということを教えられている様だ。
【中村】「古代インドの刑罰は盗みに関してはきわめて苛酷でした。ごくわずかの金銭を盗んでも死刑に処せられました。釈尊の当時のことはよくわかりませんが、おそらく同じように刑罰はきびしかったことでしょう。こういう状態であったならば、『盗むなかれ』という戒めがきびしく説かれたのは当然のことであります。」(同p331)
この教えは、現代人の我々も様々な場面でいろいろな意味に解釈できるのではないだろうか。
3.不邪淫戒
第三に、邪淫を行なうなかれ。
これは男女間の道を乱してはならぬ、ということ。拙稿12-15(夫婦の倫理参照)
4.不妄語戒
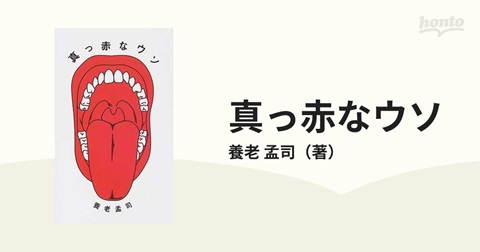
第四に、偽りを言うなかれ。
【中村】「ことばは人間にとって大切なものです。それだけにまた恐ろしいものです。『人が生れるとその口の中に斧が生じる。それによって自己を斬るのである」。ことばを慎むべし、ということは繰り返し説かれています。 ところで真実を語れ、という教えには種々の問題が残されています。
例えば重病人に向って「病は重いぞ」とありのままに語ることがいいかどうか。この問題はある経典の中で詳しく論じられていますが、「人格を完成した人は、たとい真実のことでも。相手のためにならないことであるならば、語らない」。
しかし「真実で、しかも相手のためになることであるならば、たとい相手に不愉快なことであっても、それを語ることがある」とされています。
では人はなぜ嘘をつくのか。それは何ものかを貪ろうという執着があるからです。また、人間が嘘をつくのは、特に利益に迷わされた場合が多い。それに対して仏教では、たとい雷が落ちようとも、財宝などのために、利欲心などのために、知りつつも虚言を述べることをしてはならない。」(同p332-333)

そのほか、この不妄語戒の中には、「他人の悪口や中傷を言ってはならない」「他人の過失をとがめだててはならない、人をそしってはならない」「粗暴な荒々しいことば、怒りのことばを発してはならない」「人が平常ひけ目を感じている点を指摘したり、言ったならば気分を害するようなことを口にしたりしてはならない」など仏教ではことばに関する戒めがたくさんあるが、「慈悲心」ということがその根本となっているからとされる。
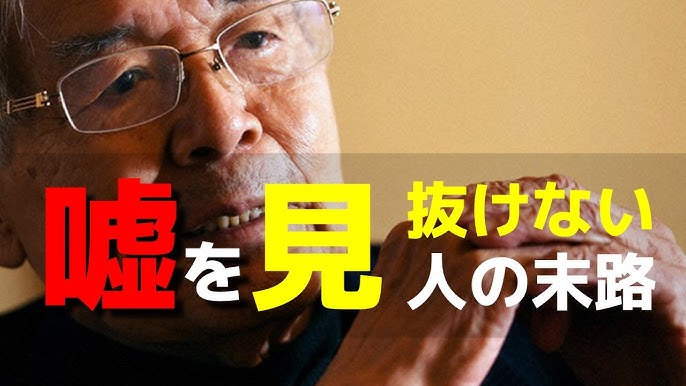
釈尊在世にヴァンギーサという長老が語ったとされるのが、
第一が、最上の善いことばを語れ。
第二が、正しい理を語れ、理に反することを語るな。
第三が、好ましいことばを語れ。好ましからぬことばを語るな。
第四が、真実を語れ。偽りを語るな。(中村元/文庫本 『ブッダのことば』p450)
【公式】養老孟司 騙しと嘘の話 〜いい物語は騙されても成立する〜
以上、4つの戒めがあるが、それに後から加えたとされるのが、第五の戒めとして、
5.不飲酒戒
酒を飲むなかれ
仏教では4つの戒めに加えて、「酒を飲むなかれ」というのをつけ加えたとされる。
これは、当時でも、人を怠惰ならしめる原因の中で最も大きなものとして飲酒が考えられていた様だ。
飲酒はまた財を浪費することになる、という点からも禁じられたとされる。
現代でも” 酒は飲んでも飲まれるな”と言われる様に今も昔も酒は人格を狂わす要因にもなるということだろう。

五戒とは関係ない様だが、
猪八戒は、中国の四大奇書小説『西遊記』に登場する主要登場キャラクターの一人である妖仙
猪八戒は、かつては天界で天の川を管理し水軍を指揮する天蓬元帥だったが、酔った勢いで美しい嫦娥に強引に言い寄り、豚として地上に落とされた。
怠慢で大食い。さらに最悪なことに好色だとされる。