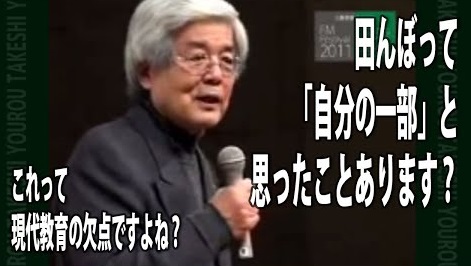⑨ なぜ他人を愛するのか
釈尊が主張した、何ゆえに 人は他人を愛すべきであるか、他人と気持をともにすべきなのか、について、中村先生の解説では、
人は何人といえども自己を愛している、また自己を愛さなければならない

「自己を愛するということが、まず自分を確立して行動を起す出発点なのです。この事実をはっきり認める。
何人にとっても自己よりもさらにいとしきものはなし
自分というものがあれば、その人にとってはその自分というものが最もいとしきものであり、最も大切なものである。そして そのことは他の人にとっても同様である、ということになります。」
(中村元 原始仏典を読むp289-290)
続いて
同様に他の人々にもそれぞれ自己はいとし、故に自己を愛するものは他人を害すべからず
(パーリ原典協会本『サンタユッタ・ニカーヤ』第一巻p175、『ウダーナ』5.1)
すべての人々は生を愛し、死をおそれ、安楽を欲している、だから自己に思いくらべて他人を殺してはならぬ、また殺きしめてはならぬ
かれらもわたくしと同様であり、わたくしもかれらと同様であると思って、わが身に引きくらべて、(生きものを)殺してはならぬ。また他人をして殺させてはならぬ。(文庫本『ブッダのことば』p705)
「自己を守るということが出発点となって、今度は他の人を守るということになります」
自己を守る人は他の自己を守る、それ故に自己を守れかし。
(パーリ原典協会本『アングッタラ・ニカーヤ』第三巻p373)
ここでいう「自己を守る、自己を実現する」ということについて、中村先生は、
「この場合に説かれている自己というものは、もはや相対立し相争うような自己ではない。
つまり、一方の犠牲において他方が利益を得るという、そういう意味の自己ではない。むしろ他人と協力することによってますます実現されるところの自己であります。
自分と他者とが対立している、その対立が発露されるという場合に真実の自己の利が実現されます。
仏典の中では、『自己の利をはかれ。自己の利を実現せよ』、というような文句さえもあります。
それは、世人がしばしば誤解するように、単に自分の財産をふやすとか、自分の世俗的な利益をはかるという意味ではないのです。当然そういうことも付随してきますが、自己と個人とがお互いに連関し合って生存している。その場において自己を生かすということは、他人を生かすということになる。
個人から切り離された自己というものは、実際問題としてはありえないのです。」(中村元著 原始仏典を読むp291-2)
誰人も運命をともにしている
現実問題として、我々はこの日本と言う国に生まれ住んでおり、この限られた国土に日本社会を形成していることは、誰人たりとて運命をともにしていることになるわけだ。
土から生まれ土に還る

中村先生はそのことについて、
「そしてその国土に産する産物によってわたくしどもは養われているのです。けれどもその産物ができるのはなぜかというと、実に無数の多くの人々が働いてくれるからです。
それだけでは十分ではありません。さらにそこに太陽の熱であるとか、自然の力というものが働いている。太陽の熱などというものは地球上のものではなく、遠い彼方から来るのです。その力が働いている。
そういうことを思いますと、わたくしどもの存在というものは、遠い彼方の、光で到達するにしても何万年もかかるような遠い彼方の力さえも及んでいる。もうお互いに目に見えない因果の網によってしっかりと結び合っている、いわば運命の共同があるわけです。
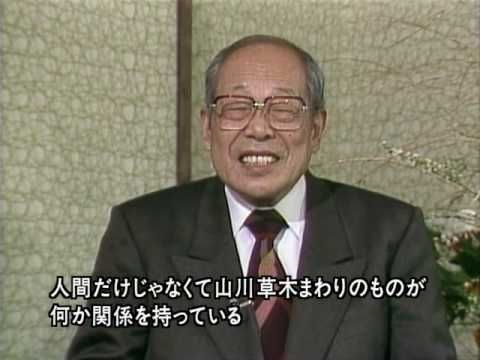
それに気づかない間は、他人は他人だ、オレは オレだ、無関係だということになりますが、お互いに置かれている運命を反省してみて、その因果の連鎖の網をずっとたどっていきますと、お互いに結び付いている。 」(中村元著 原始仏典を読むp292)
オレはオレの現代人

確かに、そう考えると、お互いの存在というのは決して孤立したものではないことになるが、悲しいかな、現代人ほど他人から切り離され孤立し孤独であると思い込んでいる人も多いと思う。
また、他人なんか構ってられない、自分の人生は短く一回きりだから、自分が楽しく幸せであればよい、他人を犠牲にしてでもと考えている人も多いのではないかと感じられる。
宇宙の法則の中の一員だと思えば孤独どころか、自分の役割も見えてくるがそれを自覚できないのもまた人間だということだ。
この自分は一人だという考え方は西洋思想の神と自分という思想から来るのだろう。
江戸時代までの日本は5人組制度というのがあって、5人一組で互いを面倒見ていたといわれる。
しかし、明治維新以降、西洋思想を取り入れて行くにつれ、いつしかそれまでの日本独自の仏教から来る思いやりや慈しみなども薄れてしまった様だ。
特に、大戦の敗戦後に一気に米国からの食物が供給されトルーマン政策なるものも影響したのだろうか、すっかり自分さえ楽しければの思想なき国民性になったと感じる。
つながって生きている/養老孟司

養老孟司先生が同じことを言っているので紹介する。
土から生まれ土に還る
【養老】「人間に限らず生き物は、すべてがつながっているんですよ。 たぶん今の人は、昔の人とかなり違うところがあるとすれば、「一人で 生きている」という感じじゃないですか。
「個人」というのが強くなって きていると思うんです。
戦争中のことを言うと、あの時代はあとに残った者のため、仲間のた め、家族のためという、個人の生き方というよりも集団の生き方をしていた。つまり「つながっている」という感覚が強かった。
昭和20年までは、少なくとも日本 の民法で家制度というのがありましたよね。今それがきれいに消えました。なぜかと言うと、社会が人は個で生きるというふうに作っているからなんです。戦争が大きな原因でしょ。
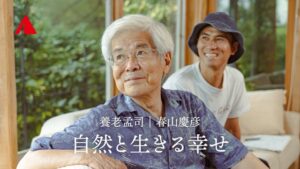
非常にはっきりしているのは、「田んぼっていうのは将来のあなたでしょ」ということが分からないんですよ。つまり、田んぼに稲が育って米が出来て、その米を食べるとそれが自分の体になるわけでしょ。だから田んぼは将来の自分なんだという感覚。そんな感覚はもう全くないで昔は、人は土から生まれて土に返るって言ったでしょ。今は病院で生まれて病院で死んでますからね。魚を食べたら海をそのまま食べているっていう感覚。我々はいやだってつながってるんだけど、そういう感 覚がなくなっちゃってる。」